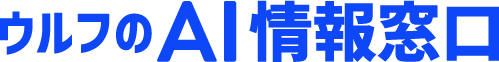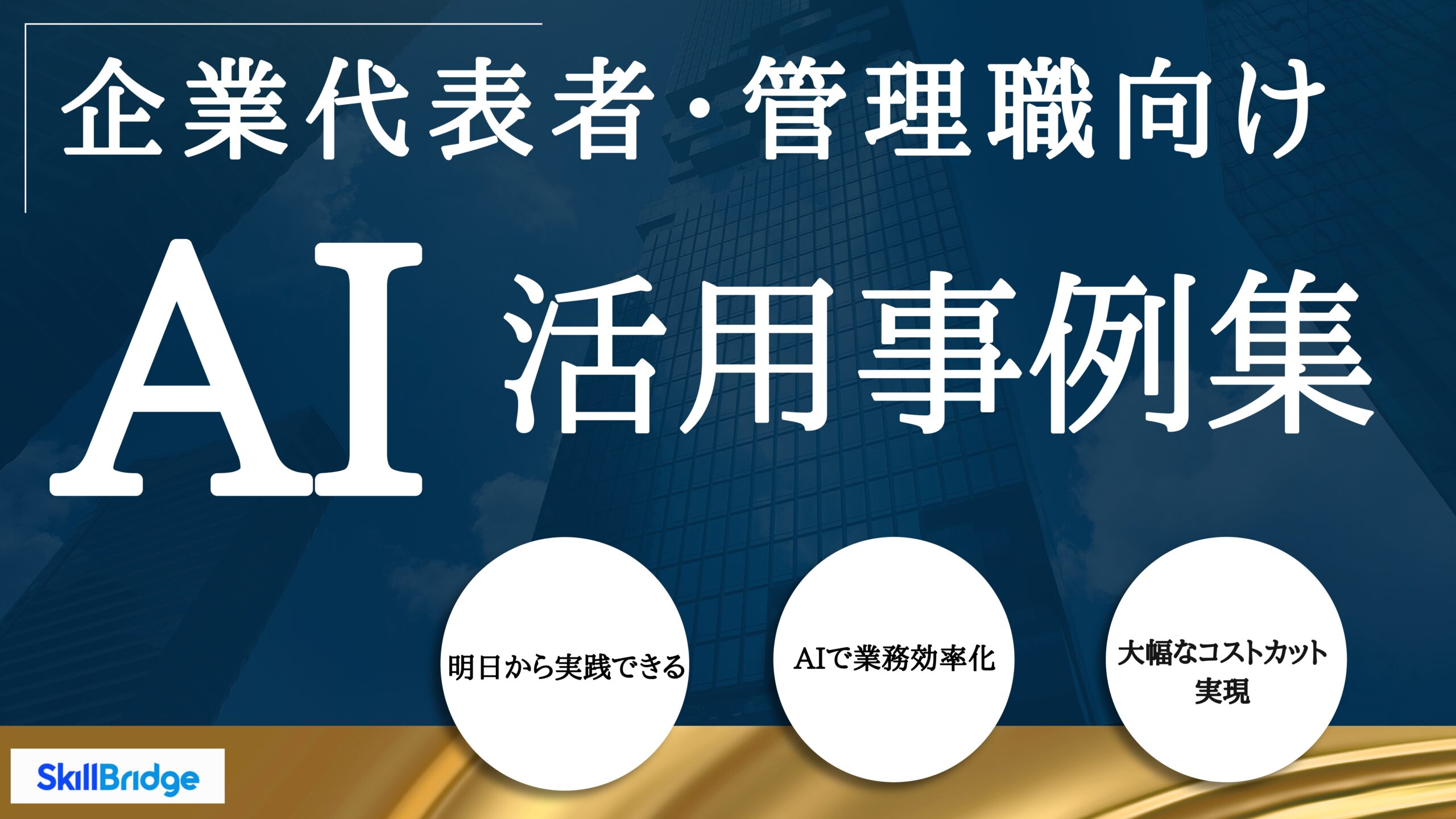そもそも「生産性」とは何か
「生産性を向上させたい」と考える方は多いでしょう。しかし、生産性について正しく理解できているでしょうか。
まずは、生産性とは何かについて、詳しくみていきましょう。
生産性には2種類ある
生産性とは、限られた資源やコストを活用して、どれだけ多くの成果を生み出せるかを示す指標のことです。
基本的に、「アウトプット(生産量や成果)」を「インプット(人員や資源、労働時間数)」で割ることで計算されます。
この生産性には大きく分けて2つの種類が存在します。
「付加価値額」を「労働量」で割ったもので、特に情報やサービスといった無形商材を扱う業界でよく用いられる指標です。例えば、IT業界では開発されたソフトウェアがどれだけの価値を生み出したかを測る際に使われます。
「生産量」を「労働量」で割った指標で、製造業など目に見えるものを作る場面で多く利用されます。例えば、工場での製品生産数を労働者数や労働時間で割ることで、生産性を把握できます。
このように、業界や状況によって使われる指標が異なるため、自分の業務に合った視点で生産性を見直すことが重要です。
生産性向上と業務効率化は違う?
生産性向上と業務効率化は、似ているようで異なる概念です。
業務効率化とは、作業の無駄を省き、必要なプロセスを簡潔にすることを指します。
これによって、労働投入量(従業員数や労働時間)を適正化することができます。その結果、同じ労働量でもより多くのアウトプットを生み出せるようになり、生産性向上につながります。
例えば、デジタルツールを活用して手作業を減らしたり、作業フローを見直したりすることで効率化を図れます。
このように、「どうすれば効率良く作業を進められるか」を考えることが、生産性を高める第一歩です。
生産性向上が求められる理由
生産性向上が注目される背景には、社会や経済の変化に伴う重要な課題が存在します。
下記で、その代表的な3つの事態について解説します。
労働力人口の減少が続いている
少子高齢化の影響で、生産年齢人口が減少し続けています。この傾向は、日本の労働市場全体に大きな影響を与えています。
具体的には、従業員一人ひとりの業務効率を高めなければ、経済の安定や成長が難しくなる状況です。限られた人材で成果を最大化することが求められています。
国際競争力が低下している
世界規模での競争が激化するなか、日本の生産性は他国に比べて低いことが指摘されています。
このままでは、国際市場での競争力を維持することが難しくなるため、企業は効率的な運営や新しい技術の活用を通じて、グローバルな市場で優位性を築く必要があります。
働く人の意識が変わってきている
近年、働き方に対する価値観が多様化し、従業員は効率的かつ柔軟な働き方を求めています。
企業は従来の労働スタイルを見直し、労働環境の改善やスキルアップ支援を通じて生産性の向上を図ることが重要になっています。
生産性向上を実現する5ステップ
生産性を向上させるには、大きく分けて「投入を減らす」か「産出を増やす」の2つの方向性があります。
無駄なインプットを削減する具体的な手順を5つのステップに分けて解説します。
1. 現場の生産性を可視化する
生産性とは、「産出÷投入」で表されます。まずは、現在の状態を数値として把握することが重要です。
産出(成果)と投入(時間や労力など)の量をそれぞれ明確にし、現場の生産性を可視化しましょう。
このプロセスを通じて、改善が必要なポイントが見えてきます。
2. 組織ごとの業務内容やプロセスを整理する
組織内のタスクをすべて洗い出し、どのような業務が行われているかを整理しましょう。この際、重複している業務や無駄と思われる作業を見つけることが大切です。
また、業務フローが滞っている箇所を特定することで、ボトルネックを発見できます。
現場メンバーへのヒアリングやアンケート調査を活用すると、実態をより具体的に把握できます。
3. 業務をノンコア業務とコア業務に切り分ける
業務を「コア業務」と「ノンコア業務」に分類しましょう。
コア業務は、自社で対応するべき重要な業務を指します。一方で、ノンコア業務はルーチン作業や付随的な業務であり、外部に委託しても問題ありません。
例えば、経理や事務作業などをアウトソーシングすることで、コア業務に集中しやすくなり、生産性向上だけでなくコスト削減も期待できます。
4. 業務環境を整備する
効率的に業務を進めるためには、適切な業務環境を整えることが欠かせません。特に、ITツールの導入は有効な手段です。
例えば、勤怠管理システムや給与管理ソフトを活用することで、作業負担を大幅に軽減できます。試験導入などを通じて現場の声を聞きながら、最適なツールを選びましょう。
5. 目標値を決めPDCAを回す
最終的には、目標となる数値を設定し、それを達成するための計画を立てます。そして、計画(Plan)、実行(Do)、検証(Check)、改善(Act)のサイクルを繰り返しながら目標に近づけていきましょう。
例えば、売上や時間当たりの生産量など、具体的な指標を用いると進捗を把握しやすくなります。
全体を俯瞰しながら、部分的な改善が全体に良い影響を与えるよう連携させることが重要です。
生産性向上の取り組み5選
最後に、企業が取り組むべき生産性向上の5つの取り組みについて具体的に紹介します。
最新テクノロジーを活用する
最新テクノロジーによる自動化や効率化によって、生産性が見込めます。
例えば、近年注目されているRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、定型的な事務作業を自動化できる技術です。導入によって、作業時間を削減しながら、ヒューマンエラーを防ぐことが可能になります。
また、AIや機械学習を活用した需要予測や在庫管理も普及しつつあります。これらの技術は、データにもとづいた効率的な意思決定をサポートし、より精度の高い業務運営に役立ちます。
人材配置を適正化する
適切な人材を適切な業務に配置することは、生産性を向上させる重要なポイントです。
従業員それぞれのスキルや経験、資格情報を一元管理し、それに基づいた配置を行うことで、無駄な労力を省き、効率的な業務運営が実現します。
また、適正な人材配置は従業員の満足度向上にもつながり、結果的に長期的な生産性アップに寄与します。
アウトソーシングを活用する
企業の利益に直接関係しない事務作業などの業務は、外部に委託することで、従業員が本来注力すべき業務に集中できる時間を生み出せます。
さらに、RPAでは対応が難しい複雑な業務についても、専門知識を持つ外部企業に任せることで、効率化を図ることができます。限られたリソースを有効活用するための有力な手法です。
社員同士のコミュニケーション機会を増やす
従業員間のコミュニケーションを活発にする場を設けることは、組織全体の連携を強化するうえで重要です。
例えば、部署を超えた交流の場や勉強会を開催することで、新しいアイデアの共有や問題解決のスピードアップが期待できます。
このような取り組みは短期的な成果が得られないかもしれませんが、長期的には組織全体の生産性向上が見込めます。
従業員のスキルアップを図る
資格取得支援や研修制度を導入し、従業員が自分のスキルを向上させられる機会を提供することも、生産性向上には欠かせません。
例えば、ワンランク上の業務に挑戦できるような環境を整えることで、個々の成長を促します。
なお、その一貫としてeラーニング「SkillBridge」も役立ちます。
SkillBridgeでは、生成AIの基礎から実践までを効率的に学ぶことが可能です。生成AIを使いこなせば、業務の効率化や生産性の向上が期待できます。
生成AIの導入を検討している企業様は、ぜひご検討ください。
まとめ
生産性向上は、企業が限られたリソースを最大限活用し、競争力を高めるために欠かせない取り組みです。現状の可視化や業務整理、最新技術の活用といった実践的なステップを踏むことで、効率的かつ継続的な改善が可能になります。
自社に最適な取り組みを見つけ、生産性を高めていきましょう。