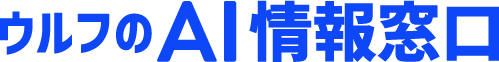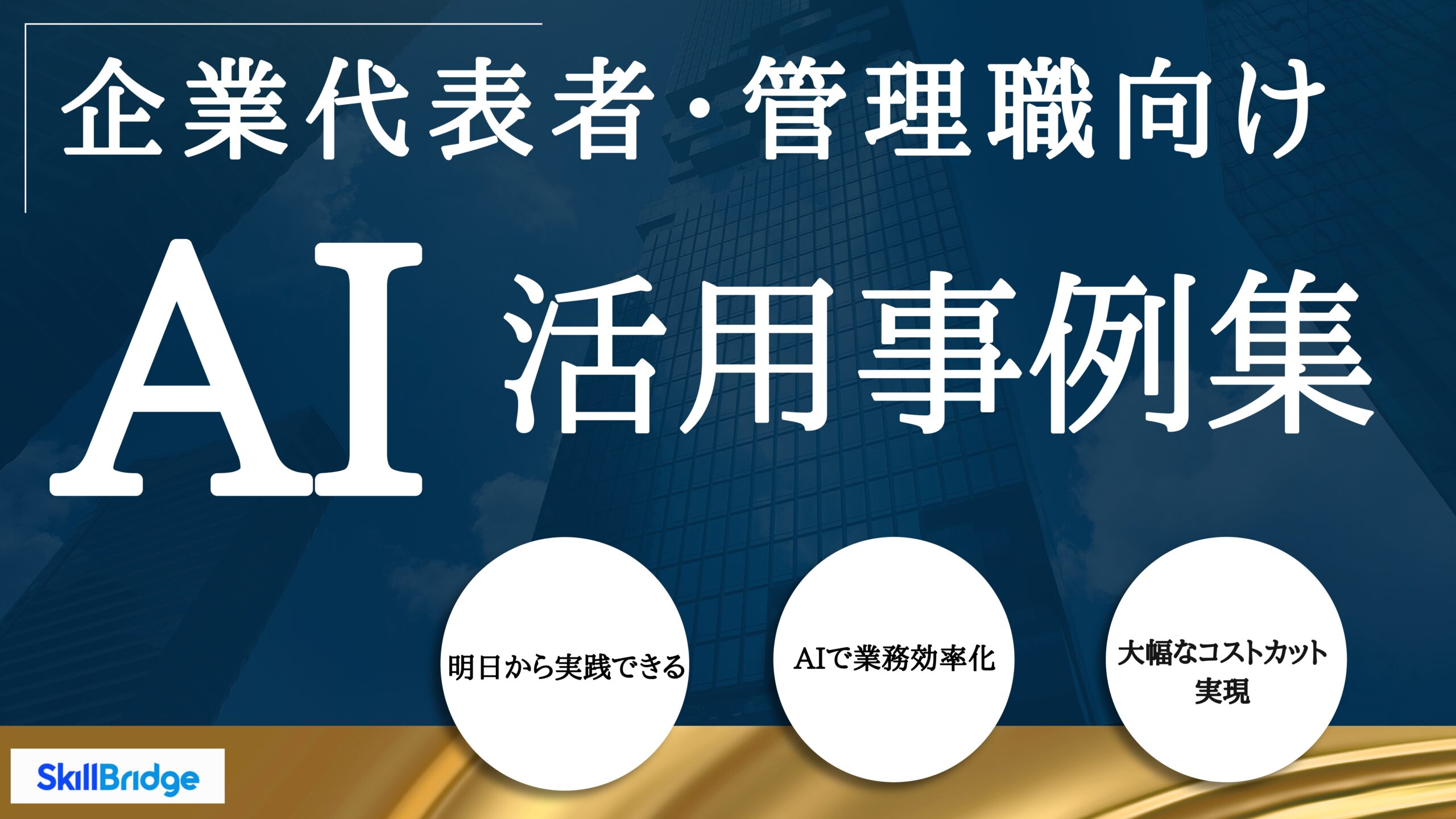作業効率が低いときの主な原因
作業効率の低下には明確な原因があります。これらを理解し対策することで、組織全体の生産性を向上させることが可能です。
まずは、作業効率が低下する主な要因をみていきましょう。
長時間労働
人手不足やコスト削減を理由に少ない人員で業務を回すと、長時間労働や深夜残業が常態化することがあります。単に時間が長くなるだけでなく、集中力の低下や疲労の蓄積により、ミスの増加やパフォーマンスの低下を招きます。
また、長時間労働は従業員の心理面にも悪影響を及ぼし、仕事へのモチベーションを低下させる原因になります。
属人化
業務の属人化とは、特定の担当者がいないと業務が進まない状態のことです。このような環境では、担当者の休暇や病欠、さらには離職によって業務が完全に停滞してしまうリスクがあります。
また、知識やスキルの共有が行われないため、組織全体のスキル向上も妨げられます。
マルチタスク
現代ではマルチタスクが求められることもありますが、多くの場合、複数のタスクを同時に処理すると効率は低下します。
タスク切り替えのたびに集中力が途切れ、ミスをする確率が高まります。また、脳への過剰な負荷がかかることで、作業者のストレスや疲労感が増加し、長期的なパフォーマンス低下につながります。
アナログな環境
アナログな業務環境は、作業効率を大幅に低下させます。例えば、紙ベースの決済システムでは承認プロセスに時間がかかり、進捗状況の管理も困難です。
また、デジタルツールの自動チェックや修正機能がなければ、手書きや手計算でのミスが発生しやすくなります。書類の印刷・郵送・署名といった物理的な手続きにも余分な時間がかかり、業務全体のスピードが低下します。
無理なデジタル化
システム導入によるデジタル化を進めている企業でも、逆に生産性が低下するケースがあります。このような状況が発生する原因として、従業員のデジタルリテラシー不足や、自社の実際の課題に合わないシステムの導入があげられます。
結果として、新しいツールの操作に時間を取られたり、既存の業務フローとの不整合が生じたりして、全体の効率が悪化するでしょう。
作業効率を上げる具体策8選
ここでは、作業効率を高めるための施策を8つ紹介します。
ワークフローを見直す
業務の流れを最適化することで、無駄な工程を排除し、効率を高められます。まず、現状のワークフローを可視化し、下記の観点で分析しましょう。
・不要な業務や重複している作業はないか
・複数の担当者で分担したほうが効率的な業務はないか
・専門性を活かすために、担当者の変更が必要な業務はないか
ワークフローを見直す過程で、自動化できる業務や外注候補の業務もリストアップしておくと、その後の施策立案がスムーズに進みます。各部門の特性に合わせたワークフローの最適化が、生産性向上の第一歩となります。
業務マニュアルを作成する
業務を標準化するためには、しっかりとしたマニュアル整備が効果的です。適切に作成されたマニュアルは、下記のメリットをもたらします。
・新人教育の効率化と早期戦力化
・担当者不在時のバックアップ体制強化
・業務の品質の均一化
・属人化の防止
マニュアルを作成する際は、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を明確にし、部署全体のガイドラインとして機能するよう設計しましょう。
また、マニュアルは一度作成して終わりではなく、業務の変化に合わせて定期的な見直しと更新が必要です。クラウドベースのドキュメント管理ツールを活用すれば、更新履歴の管理や関係者間での情報共有がスムーズになります。
アウトソーシングを活用する
コア業務に集中するために、専門性の高い業務や定型作業は外部リソースの活用を検討しましょう。アウトソーシングを活用するメリットは、下記の通りです。
・自社の強みに経営資源を集中できる
・専門知識やスキルを外部から調達できる
・繁忙期の人員不足を柔軟に補える
特に人事、経理、ITサポートなどの専門業務や、データ入力などの定型作業は、外部委託を検討してみる価値があります。適切な外部委託先を選び、明確な業務範囲を設定することが、成功の鍵となります。
タスク管理ツールを導入する
プロジェクトやタスクの進捗状況をリアルタイムで把握するために、タスク管理ツールの導入が効果的です。これにより、下記のような業務改善が期待できます。
・タスクの優先順位付けと期限厳守の徹底
・チーム内の情報共有の円滑化
・業務の進捗状況の可視化
代表的なタスク管理ツールとして、TrelloやAsana、Backlogなどがあげられます。部門の規模や業務特性に合わせて最適なツールを選定し、全員が活用できる環境を整えましょう。
業務を自動化する
繰り返し行う定型業務は、RPA(Robotic Process Automation/ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用して自動化することで、大幅な時間短縮が可能になります。RPAとは、パソコン上で行う業務を自動化するシステムのことです。
自動化に適した業務例は、下記の通りです。
・データ入力や転記作業
・定期レポートの作成
・請求書処理や経費精算
・顧客情報の管理や更新
RPAを導入することで、ヒューマンエラーの削減と業務スピードの向上が期待できます。さらに、AIツールを活用すれば、より高度な判断が必要な業務も一部自動化することが可能です。
コミュニケーションを効率化する
部門間や拠点間のコミュニケーションを円滑にするためには、適切なツールの導入と運用ルールの整備が必要です。スムーズなコミュニケーションを実現するためのポイントは、下記の通りです。
・用途に応じたコミュニケーションツールの使い分け
・オンラインと対面を組み合わせた会議環境の整備
・会議の目的と所要時間の明確化
Microsoft TeamsやSlackなどのビジネスチャットツールを活用し、メールとの使い分けを明確にすることで、情報伝達のスピードと質が向上します。また、会議のアジェンダ共有や時間管理の徹底も重要です。
ペーパーレス化を推進する
書類のデジタル化は、保管スペースの削減だけでなく、業務効率化にも大きく貢献します。ペーパーレス化による主なメリットは、下記の通りです。
・必要な情報への迅速なアクセスと検索機能の向上
・複数の担当者による同時編集と情報共有の円滑化
・印刷や保管にかかるコスト削減
クラウドストレージや文書管理システムを導入し、電子決裁システムと連携させることで、承認プロセスも大幅に短縮できます。導入初期はルール整備と社内教育に力を入れ、段階的に移行することが成功のポイントです。
担当者のデジタルリテラシーを高める
作業効率を高めるためには、組織全体のデジタルリテラシー向上が不可欠です。具体的な取り組みとしては、下記があげられます。
・外部研修や勉強会の定期開催
・デジタルスキルに関する資格取得の推奨
・部門横断的なDX推進チームの編成
特に、生成AI活用のスキル向上は、今後の競争力強化に直結します。
生成AIに精通した人材を育成するのであれば、eラーニングサービスの「SkillBridge」をご検討ください。
「SkillBridge」では、生成AIの基礎から応用まで、初心者でも安心しても学べるような学習プログラムを提供しております。各業種・職種に合わせて実践的なカリキュラムを用意しているため、業務で役立つ生成AI活用方法が学べます。
全社的に作業効率を高めるためのポイント
業務効率化は各部署が部分最適で進めることも多く、部署間の意識やリテラシーの差が生じるケースもあるでしょう。ここでは、企業の人事・総務担当者向けに、全社的に作業効率を高めるポイントを紹介します。
経営層が主導で推進する
全社的な業務効率化には、経営層の強いリーダーシップが欠かせません。現場の従業員だけでは日々の業務が優先され、施策が後回しになりがちです。
経営層が業務効率化の重要性や意義を現場に直接伝え、共感を得ることで社員の当事者意識が高まります。
部署横断的な思考で最適なシステムを選ぶ
各部門が個別にシステムを導入すると、部門間でのデータ連携が困難になり、かえって転記作業などの新たな業務負担が増えることがあります。効率的に施策を推進するためには、全社的な視点でシステムを導入することが不可欠です。
まずは全社で業務の棚卸しを行い、各部門が抱えている課題を整理しましょう。そのうえで、部門間の連携をスムーズにするシステムを選ぶことで、データの一元管理と業務プロセスの標準化が実現できます。
部署横断的な視点でシステム選定を行うことが、真の業務効率化につながります。
DX推進のための人材を育成する
全社的な業務効率化を持続的に推進するには、社内でDX人材を育成することが重要です。
必要なスキルは、IT関連の基礎知識にとどまらず、AIやデータ分析の知識、プロジェクトマネジメント能力、さらには周囲を巻き込むコミュニケーション力など、多岐にわたります。これらのスキルを体系的に身に付けられるよう、育成計画を立てることが大切です。
振り返りをする
業務効率化の施策を導入した後は、定期的な効果検証を行う必要があります。
業務のフローを変更したことで、これまでと異なる不具合は生じていないか、どれだけの時間短縮を実現できたかなど、具体的な数値で効果を測定しましょう。
効果検証の結果を全社で共有することで、成功事例の横展開や課題の早期発見につながります。継続的な振り返りと改善のサイクルを回すことで、持続的な業務効率の向上を実現できます。
まとめ
長時間労働や業務の属人化、マルチタスク、アナログな環境などは、作業効率を低下させる要因となります。作業効率の向上には複数の有効なアプローチがありますが、自社の課題に合わせて進めることが重要です。
また、作業の効率化は各部署の部分最適ではなく、全体最適で考えることも大切です。今回紹介したポイントをもとに、組織全体の効率化を進めていきましょう。