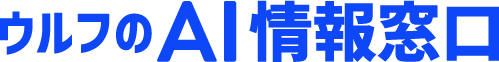属人化が起こる根本的な原因
多くの企業で属人化の解消が叫ばれていますが、その解決には根本的な原因を理解する必要があります。
ここでは、属人化を引き起こす4つの主要な原因について詳しく解説していきます。
業務の専門性が高い
高度な専門知識や豊富な経験を必要とする業務は、必然的に属人化のリスクが高まります。
例えば、特殊な技術を扱うエンジニアや、長年、取引先との関係性を築いている営業担当者などが該当します。
このような専門性の高い業務では、担当者に裁量権を与えることで効率的に進められることが多く、その結果として業務が特定の個人に依存しやすくなります。
また、専門性が高いがゆえに、適切な人材の採用が困難であり、社内での後継者育成にも時間とコストがかかります。
情報共有の仕組みが整っていない
多くの企業で、情報共有の仕組みが十分に機能していないことが属人化を助長しています。
例えば、業務フローが明確に定義されていない、グループウェアやビジネスチャットなどのコミュニケーションツールが効果的に活用されていないなどの状況です。
さらに深刻な問題として、情報共有を積極的に評価する制度や文化が根付いていないことがあげられます。
結果として、知識やノウハウなどの重要な情報が個人に留まってしまいます。
属人化がモチベーションにつながっている
一見すると、問題ばかりがあるように思える属人化ですが、実は従業員のモチベーション向上に寄与している側面もあります。
業務を一任され、大きな裁量を持って働けることは、多くの従業員にとってやりがいや責任感につながっています。
しかし、この状況は別の問題を引き起こす可能性があります。担当者が社内での存在価値を維持するために、意図的に業務の共有や引き継ぎを避けるといった弊害です。
その結果、後継者の育成が進まず、属人化がさらに深刻化するという悪循環に陥ります。
人手不足や業務過多で時間的な余裕がない
多くの企業が直面している人手不足や業務過多の状況も、属人化を促進する要因です。
業務の標準化やマニュアル作成、後継者の育成には相当な時間と労力が必要ですが、日々の業務に追われる中でそれらの取り組みが後回しにされがちです。
特に、属人化している業務を担当している従業員は多忙を極めていることが多く、知識やスキルの移転に充てる時間的余裕がありません。
このような状況が続くと、属人化を解消するための体制構築がいつまでも進まず、問題が慢性化してしまいます。
属人化の解消に重要な5つのポイント
属人化は闇雲に解消しようとするのではなく、戦略的なアプローチが必要です。
ここでは、管理職の方々が押さえておきたい5つの重要なポイントについて解説していきます。
そもそも属人化の解消が本当に必要なのかを考える
属人化というと、多くの場合「解消すべき問題」として語られることが一般的です。しかし、すべての業務において属人化を排除することが最適解とは限りません。
特に、クリエイターやデザイナー、料理人、職人といった、センスや技術が問われる職業においては、その人ならではの創造性や独自の視点が価値を生み出します。
こうした分野では、一定の属人化は付加価値の源泉となり、むしろビジネス上の強みになる可能性があります。完全に標準化してしまうと、他社との差別化が難しくなりかねません。
ビジネスにおいては「何をどこまで標準化し、何を属人的な強みとして活かすか」というバランス感覚が求められます。業務の性質や組織の状況を踏まえて、慎重な判断を行いましょう。
担当者別に業務を洗い出す
属人化の解消を進めるためには、まず現状を正確に把握することが重要です。
各担当者の業務内容、1日あたりの作業時間、業務の難易度、必要なスキルセットなどを詳細に洗い出しましょう。
この分析により、どの業務が属人化しているのか、その程度はどれほどか、また解消するためにはどのようなアプローチが効果的なのかが明確になります。
例えば、ある業務が属人化している理由が単にマニュアルの不備なのか、それとも高度な専門知識が必要なのかによって、取るべき対策は大きく変わってきます。
権限や業務を分散させる
一見複雑に見える業務でも、細分化すると複数の担当者に分散できる場合があります。
例えば、営業担当者が抱える業務を「見積作成」「顧客折衝」「契約管理」などに分解し、それぞれに適した担当者を配置するイメージです。
分散化によって、特定の従業員への過度な依存を減らすことができるだけでなく、ダブルチェックの体制を新たに構築することも可能です。
結果として、担当者の心理的負担の軽減やミスの防止に役立つでしょう。
業務改善を進めて無駄をなくす
属人化を解消する取り組みと並行して、業務プロセスの見直しや効率化も重要です。
例えば、既存の業務フローを分析し、不必要な承認プロセスの削除や、反復作業の自動化などを進めることで、業務効率を大幅に改善できます。
特に、デジタルツールの導入は効果的です。プロジェクト管理ツール、ナレッジ管理システム、コミュニケーションツールなどを活用することで、情報共有を促進し、業務の可視化を図ることができます。
従業員が属人化の解消に取り組む時間的な余裕も生まれやすくなるでしょう。
関連記事:「業務改善の具体例・アイデア11選!進め方や注意点も解説」
従業員の意識改革を進める
属人化を解消する取り組みを成功させるためには、「個人の知識は組織の資産である」という組織文化を醸成することが不可欠です。
特に管理職の立場からは、情報共有やナレッジ移転の重要性を繰り返し説明し、従業員の意識改革を目指すことが重要です。
加えて、知識やスキルの共有を促進するために、下記のような取り組みも進めることをおすすめします。
・スキルアップに積極的な従業員を評価する制度の導入
・定期的な研修の実施
・チーム間での定期的な業務ローテーション など
属人化の解消に成功した企業事例
属人化の解消は多くの企業にとって大きな課題ですが、実際に解決に成功している企業も存在します。
ここでは、異なるアプローチで属人化の解消を実現した3つの企業事例を紹介します。
業務改善により業務プロセスの標準化・効率化を実現|トヨタ自動車
トヨタ自動車の取り組みは、製造業における属人化の解消の代表的な成功事例として知られています。
同社が確立したトヨタ生産方式(TPS)は、製造現場の属人化を解消し、高品質な製品の安定供給を可能にしました。
TPSは「ジャスト・イン・タイム(必要なものを必要な量、タイミングで生産すること)」と「自働化(人の判断を機械に置き換えること)」という2つの柱を基本思想とする生産方式のことです。
この導入によって、作業手順を細かく文書化し、誰が担当しても同じ品質の製品が作れる仕組みを構築しました。
また、問題が発生した際の対応手順も標準化することで、ベテラン作業員の経験や勘に依存しない製造体制を確立したのです。
AIツールの導入により業務効率化を進める|パルコ
パルコの取り組みは、クリエイティブ業務における属人化の解消にAIを活用した革新的な事例です。
同社では、従来の広告制作は、モデル、カメラマン、デザイナーなど、各専門家の技能に大きく依存していました。
そこで、画像生成AI技術を活用して新たな広告プロモーションを展開しました。クリエイティブディレクターとAIデジタルクリエイターの指揮のもと、モデルや背景の生成はもちろん、グラフィックデザイン、動画編集、ナレーション、音楽制作までAIで実現したそうです。
これにより、撮影や音声収録などの工数を大幅に削減し、制作期間の短縮に成功しました。
モデルやカメラマンなどにかけるコストの削減効果もあり、クリエイティブビジネスの新たな手法として注目された事例です。
AIシステムの導入で業務そのものを削減する|花王
花王は、製造設備の監視業務における属人化をAIの導入によって解消した好例です。
従来、製造拠点の設備異常の検知は熟練作業員の経験と勘に依存しており、人手不足も相まって深刻な属人化が発生していたそうです。
同社は、この課題に対してAIによる異常検知システムを導入しました。
これによって、AIが24時間体制で設備の状態を監視し、異常を自動検知する仕組みを構築できたのです。人間は、AIが検知した異常の確認と対応に集中できるようになり、監視業務自体の属人化が解消されました。
さらに、AIが収集したデータを分析することで、予防保全の実現にも成功したそうです。
まとめ
属人化は、業務の専門性や情報共有の仕組み、従業員のモチベーション、人手不足など、複数の要因が絡み合って発生します。
解消のためには、業務の洗い出しから始まり、権限の分散化、業務改善、そして従業員の意識改革まで、段階的なアプローチが必要です。
まずは自社の現状を正確に把握し、できるところから着実に改善を進めていきましょう。