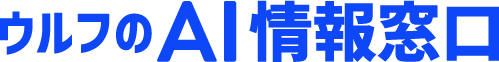【部署別】ChatGPTのビジネス活用術
まずは、全社員が使えるChatGPTの活用方法のほか、各部署の特性に合わせた活用方法を詳しく解説します。
全社員向け
社内のどの部署でも役立つChatGPTの活用方法は下記の通りです。
・Excelの関数を生成
・メールの文章を作成
・言語を翻訳
・スケジュール管理 など
Excelの関数は、自然言語で質問するだけで、適切な関数を提案してくれます。複雑な計算式や条件分岐を含むものも対応可能です。
ビジネスメールの作成では、状況や目的に応じた適切な文面を提案するため、業務効率化に役立ちます。より効果的なコミュニケーションをサポートします。
営業部署向け
営業部署のノンコア業務を効率化する、ChatGPTの便利な使い方を紹介します。
・営業資料の作成(提案資料、プレゼン資料、ホワイトペーパー)
・トークスクリプトの作成
・商談議事録の要約作成
・営業メールの文章生成
・市場調査 など
提案資料やプレゼンテーション資料の作成では、業界や顧客に合わせた資料作成を支援し、既存資料の内容チェックや改善提案も可能です。
また、商談後の議事録から重要ポイントを抽出し、簡潔な要約を作成することで、情報共有の効率化が図れます。
マーケティング部署向け
マーケティング部署では、次のような方法が役立つでしょう。
・競合調査
・ペルソナ作成
・カスタマージャーニーマップの作成
・ホットリードのリストアップ
・コンテンツマーケティングの支援 など
競合分析や市場調査のほか、具体的なペルソナ設定では、年齢、性別、役職、業種などの基本情報から、直面している課題まで詳細に設定できます。
カスタマージャーニーマップの作成では、顧客との接点から成約までのプロセスを可視化し、効果的な施策立案をサポートします。
制作部署向け
制作部署の業務効率を上げるなら、下記のような活用方法があります。
・コーディングチェック
・動画や画像の作成補助
・商品名やキャッチコピーの作成
・デザインアイデアの提案 など
コーディングのチェックや改善提案、広告用の画像や動画の作成補助など、幅広い業務をサポートします。
また、では、建築、服飾、アクセサリーなど、さまざまな分野でのデザインアイデアを提供するため、クリエイティブの発想を広げることにも役立ちます。
人事・採用部署向け
ChatGPTの次のような活用で、人事・採用業務の質向上も目指せます。
・求人広告の作成
・書類選考の評価
・採用面接の質問作成
・研修や教材のアイデア提供
・リファレンスチェック など
採用活動では、魅力的な求人広告の作成から、応募書類の評価基準に基づいた書類選考まで、一連のプロセスを効率化できます。
社員教育では、新入社員研修やスキルアップ研修のカリキュラム設計に活用でき、効果的な教育プログラムの立案に役立ちます。
ChatGPTを安全にビジネスに活用するための注意点・ポイント
企業でChatGPTを活用する際には、いくつかの重要な注意点があります。
安全な活用のために押さえておくべきポイントを解説します。
ハルシネーションへの対策
ChatGPTには「ハルシネーション(AI幻覚)」と呼ばれる現象があります。これは事実と異なる情報を、まるで本当のことのように回答してしまう特性です。
例えば、存在しない製品の詳細な仕様を説明したり、実在しない法律の条文を引用したりすることがあります。
特に注意が必要なのは、これらの誤った情報が非常に説得力のある形で提示されることです。
専門用語を交えた詳細な説明や、具体的な数値を含む回答であっても、完全な誤情報である可能性があります。
この対策として効果的なのは、ChatGPTへ質問する際に信頼性のあるデータを提示した上で、「○○年以降のデータに基づいて回答してください」といった具体的な条件を指定することです。
また、重要な業務判断に関わる情報については、必ずダブルチェックのフローを設置しましょう。
著作権侵害の予防
ChatGPTの出力をビジネスで活用する際は、著作権の問題に注意を払う必要があります。
AIが生成した内容であっても、既存の著作物を学習データとして使用している場合、類似した表現や構成が生成される可能性があるためです。
これをそのまま使用すると、意図せず著作権侵害となるリスクがあります。
このため、ChatGPTを使用する際は、必要に応じて表現を変更したり、構成を見直したりする作業が必要です。
特に、公開を前提としたコンテンツでは、専門家にチェックを依頼するなどより慎重な確認が必要です。
ChatGPTをはじめとするAIの著作権違反については、下記の記事でも詳しく解説しています。
「AIの著作権に違反しないための企業がすべき対策5選」
情報漏洩への対策
情報セキュリティの観点から、ChatGPTへの入力内容には細心の注意が必要です。入力された情報は、AIの学習データとして使用される可能性があるためです。
実際に、企業の機密情報や、社内会議の内容が漏洩した事例も報告されています。
特に注意すべきは、一見して機密情報と判断できないような内容でも、複数の情報を組み合わせることで重要な情報の推測が可能になるケースがあることです。
例えば、社内の人員配置や業務フローに関する何気ない質問でも、セキュリティ上のリスクとなる可能性があります。
これらの対策として有効なのは、企業内での明確な利用ガイドラインの策定と、セキュリティが強化されたエンタープライズプランなどの活用です。
また、入力内容の事前チェック体制を確立し、不適切な情報が入力されないよう監視することも重要です。
ChatGPTの情報漏洩に関する具体的な注意点や対策については、下記の記事でも詳しく解説しています。
「ChatGPTの情報漏洩リスクに企業はどう対処すべき?事例や対策を紹介」
従業員へのリテラシー教育
ChatGPTを企業で安全に活用するためには、従業員への適切な教育が不可欠です。
単にツールの使い方を学ぶだけでなく、生成AIの特性や限界についての理解を深めることが重要です。
具体的には、適切なプロンプトの作成方法、情報セキュリティの基礎知識、著作権に関する理解などが必要です。
定期的な研修や事例共有を通じて、従業員全体のAIリテラシーを向上させることで、より安全で効果的な活用が可能になります。
AIリテラシーに関する従業員教育のポイントは、下記の記事をご覧ください。
「AIリテラシーとは?従業員教育の重要性やポイントを詳しく解説」
まとめ
ChatGPTの活用は企業にとってメリットが多い一方で、導入には注意点もあります。
精度の高いモデル選びでハルシネーションのリスクを避け、著作権侵害や情報漏洩を防ぐための対策を徹底しましょう。
また、従業員教育を通じて、生成AIリテラシーの向上を図り、安全に業務で活用できる環境を整えることが重要です。