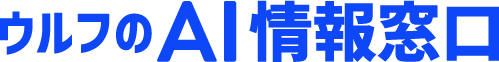ペーパーレス化の事例5選
ペーパーレス化は、業務効率の向上やコスト削減、環境負荷の低減など、多くのメリットがある一方で、導入時の混乱やトラブルを懸念する声も少なくありません。
一方で、実際に多くの企業が成功を収めています。
まずは、具体的な導入事例を通じて、ペーパーレス化の効果と成功のポイントをみていきましょう。
電子契約システムの導入により契約業務を効率化
A社では、膨大な契約業務の非効率性が大きな課題でした。
従来は、PCで作成した契約書を印刷し、印鑑管理部署での押印を経て郵送するという煩雑な手順を踏んでいました。また、大量の契約に伴う印紙税も大きな負担となっていたようです。
同社は、電子契約システムを実際の操作で比較し、「使い勝手の良さ」で従業員からの支持が最も高かったシステムを採用したことで、スムーズな移行を実現しました。その結果、労働時間とコストの大幅削減に成功しました。
会議資料の電子化により会議時間を短縮
B社では、役員会議の長時間化と会議資料準備の負担が深刻な問題でした。
特に、紙の資料を使用していたため、資料修正や差し替えが発生するたびに再印刷と配布が必要となり、時間と手間がかかっていたようです。
そこで同社は、タブレットで利用できるペーパーレス会議システムを導入しました。
このシステムにより、役員が事前に資料を確認できるようになり、また会議中の資料共有もスムーズになったそうです。
その結果、従来は半日以上を要していた役員会議を1時間半にまで短縮できました。資料作成担当者の準備時間も大幅に削減されたとのことです。
請求書の電子化により作業時間を短縮
C社は、コロナ禍でのテレワーク推進にともない、請求書の印刷・郵送作業が大きな負担でした。
特に月末の請求書発行時期には、出社して作業を行う必要があり、テレワークの妨げとなっていたそうです。
同社は、帳票作成サービスを導入し、請求書のペーパーレス化を実現しました。これにより、請求書作成から送付までの作業時間を従来の1/5まで短縮できたそうです。
また、郵送費用の削減だけでなく、顧客側での受け取り確認も容易になり、双方にとってメリットのある改革となりました。
年間100万枚の書類を削減
D社は、人工知能型ERPシステム(統合基幹業務システム)の導入により、大規模なペーパーレス化を実現しました。
同システムは、領収書をスマートフォンで撮影するだけで、AIが自動的に内容を認識し経費明細を作成するものです。従業員の手作業による入力業務を大幅に削減する効果が期待できます。
この取り組みにより、年間100万枚に及ぶ書類の削減に成功したそうです。加えて、保管スペースの確保や文書管理の手間も大きく軽減され、同時にテレワーク環境の整備も進みました。
さらに、経費精算の正確性も向上し、経理部門の業務効率化にも貢献しています。
自治体広報誌の校正業務が改善
E町の役場では、広報誌の校正業務における非効率な運用が課題でした。
紙での校正作業は、修正箇所の集約や履歴管理が困難で、担当者間での情報共有にも支障をきたしていたそうです。
そこで、クラウド型のペーパーレス会議システムを導入し、広報誌の校正プロセスを電子化しました。
これにより、複数の担当者が同時に校正作業を行えるようになり、修正履歴も自動的に管理されるようになったそうです。
その結果、校正紙の再印刷の手間も省くことができ、校正期間を短縮できました。また、役場内の会議での活用で、年間約10万枚もの紙のコストも削減できたそうです。
ペーパーレス化の推進でよくある課題
ペーパーレス化を進める際に、いくつかの課題に直面することがあります。スムーズな移行を実現するためにも、事前の対策が必要です。
ここでは、多くの組織で共通して見られるペーパーレス化の主な課題とその対応策について解説します。
ITリテラシーの不足
最も一般的な課題のひとつが、従業員間のITリテラシーの差です。
特に、紙での業務に慣れた従業員や、デジタル機器の操作に不安を感じる従業員にとって、新しいシステムの導入は大きな負担となる可能性があります。
この課題に対しては、段階的なアプローチが効果的です。
まず、分かりやすい操作マニュアルを整備し、基本的な操作から応用的な使い方まで、体系的に学べる環境を整えましょう。自社研修を行うのもひとつの手です。
また、専門のサポートチームを設置し、導入初期の問い合わせに迅速に対応できる体制を構築することも重要です。
さらに、部署ごとにITに詳しい担当者を「デジタルリーダー」として任命し、日常的な相談窓口として機能させることで、円滑な移行を実現しやすくなります。
電子化への抵抗
もうひとつの重要な課題が、ペーパーレス化そのものへの心理的な抵抗です。
「電子化すると重要な情報が失われる」などの不安や、長年培った業務習慣を変えることへの抵抗感を持つ従業員も少なくありません。
この課題を克服するためには、まずペーパーレス化の必要性と具体的なメリットを丁寧に説明することが重要です。
例えば、期待できる削減額や作業時間の短縮効果を具体的な数字で示したり、他社の成功事例を共有したりすることで、理解を深めることができます。
また、実際のシステムを体験できるデモンストレーションや試用期間を設けることも効果的です。
小規模なテストグループで先行導入を行い、その成功体験を組織全体で共有することで、抵抗感を和らげやすくなります。
ペーパーレス化を成功させる4つのコツ
ペーパーレス化は、準備不足のまま進めるとさまざまなトラブルを引き起こす可能性があります。
ここでは、確実に成果を上げるための4つの重要なポイントを解説します。
紙を利用している業務を洗い出す
ペーパーレス化の第一歩は、現状の正確な把握です。社内のどの部署で、どのような書類が、どのような目的で使用されているのかを詳細に調査する必要があります。
契約書、請求書、申請書類、会議資料など、すべての紙書類について、その発生源から最終的な保管場所まで、業務フローを可視化することが有効です。また、それぞれの書類の重要度、法的要件、保管期間なども確認しましょう。
その上で、優先的に電子化すべき書類や、紙での保管が必要な書類を明確化することが大切です。
一部の部署などで段階的に導入する
ペーパーレス化は、組織全体に大きな影響を与える改革です。
特に、取引先との契約手続きなど、社外との関係も考慮する必要があるため、一度にすべての業務を電子化することは避けるべきです。
まずは影響範囲が限定的な部署や業務から始め、そこでの成功体験を積み重ねていくことをおすすめします。
例えば、社内で完結する業務(社内の会議資料や決裁書類など)から着手し、問題点の洗い出しと改善を重ねた後に、取引先との契約書類や請求書などの電子化に進むなどの段階的なアプローチが効果的です。
導入するシステム・ツールを選定する
ペーパーレス化を実現するためには、適切なシステムやツールの選定が重要です。
導入を検討すべき主なシステムには下記のようなものがあります。
・ワークフローシステム
稟議や各種申請の電子化に活用できます。承認プロセスの可視化や処理状況の把握が容易になり、業務効率が大幅に向上します。
・電子契約システム
契約書の作成から締結までをオンラインで完結させることができ、印紙税の削減や締結までの時間短縮が期待できます。
・ペーパーレス会議システム
資料の事前共有や会議中の円滑な進行をサポートし、会議時間の短縮と資料作成の効率化を実現します。
そのほか、クラウド勤怠管理システムやファイル共有サービスなど、業務内容に応じて適切なツールを組み合わせることで、より効果的なペーパーレス化が実現できます。
ペーパーレス化の必要性を浸透させる
ペーパーレス化の成功には、組織全体の理解と協力が不可欠です。特に経営層の理解と支援を得ることは、プロジェクトを推進する上で極めて重要です。
経営層に対しては、コスト削減効果、生産性向上、環境負荷低減といった具体的なメリットを、数字を交えて説明することが効果的です。
また、競合他社の動向や、働き方改革への貢献度なども、説得力のある材料となります。
一方、現場の従業員に対しては、業務効率化による残業時間の削減や、場所を問わない働き方の実現など、個人レベルでのメリットを強調することで、前向きな協力を得やすくなります。
定期的な説明会や研修を通じて、組織全体でペーパーレス化の意義を共有していくことが重要です。
まとめ
ペーパーレス化は、業務効率の向上やコスト削減、環境負荷の低減など、組織に大きな価値をもたらす取り組みです。適切な準備と段階的なアプローチを取ることで、確実に成果を上げることができます。
導入に際しては、現状の業務分析から始め、適切なツールの選定、従業員の理解促進まで、計画的に進めていくことが重要です。
まずは自社の状況を確認し、できるところから着実に一歩を踏み出してみましょう。
関連記事:「業務改善の具体例・アイデア11選!進め方や注意点も解説」