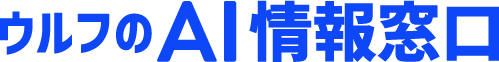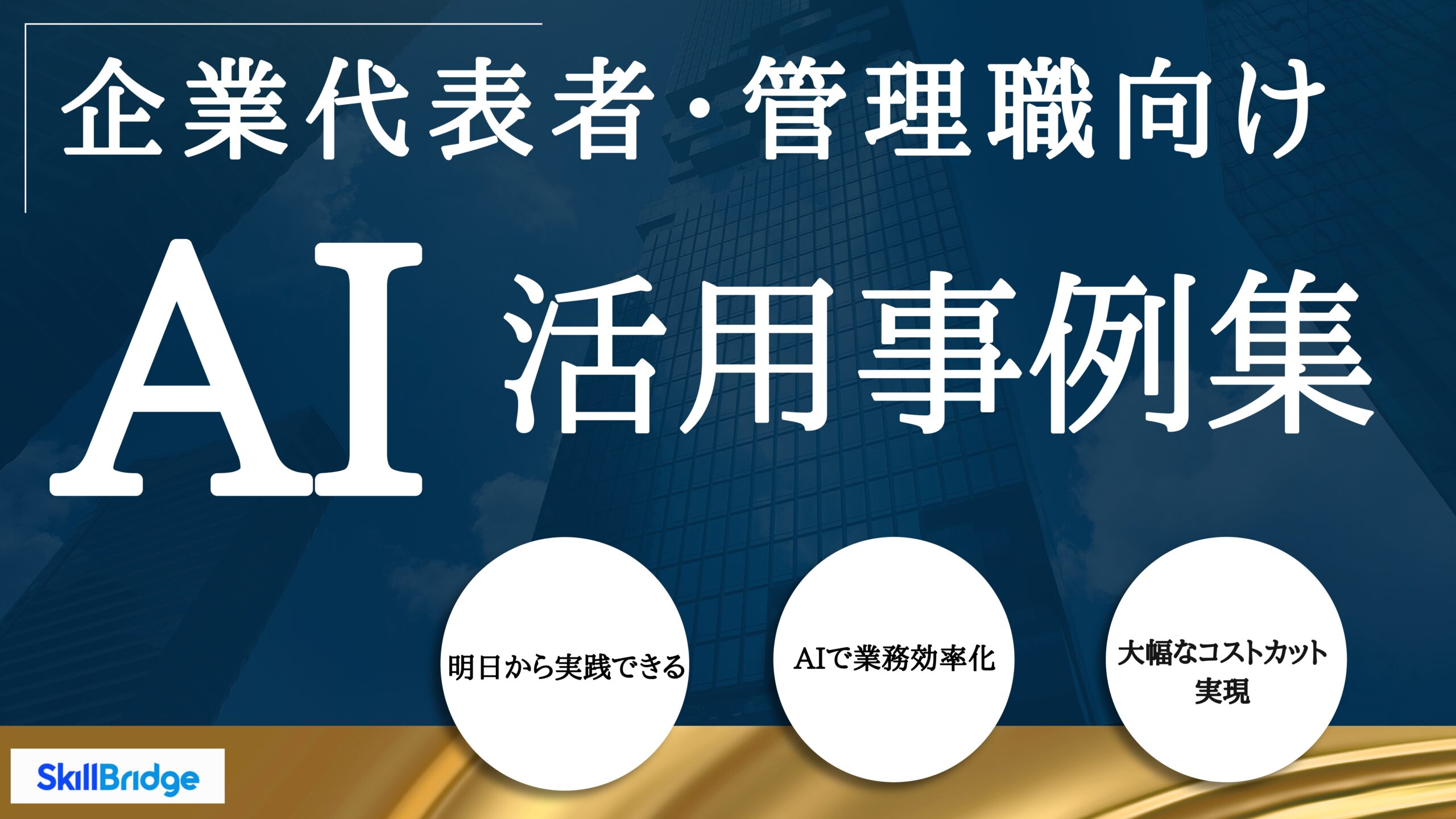AIで生成したコンテンツは著作権に違反するのか?
AI技術の進歩にともない、著作権に関する議論が活発化しています。文化庁では、AI生成物に対する現行法の扱いを明確にするための取り組みが行われており、令和5年6月、また令和6年8月に「AIと著作権」に関するセミナーが開催されました。
このセミナーでは、生成系AIの利用が場合によっては著作権侵害とみなされる可能性があることが公表されています。
そこでまずは、AIを利用して生成したコンテンツの著作権に関する考え方や、どのような場合に著作権侵害が成立するのかについて、詳しく解説します。
出典:
文化庁「令和5年度 著作権セミナー AIと著作権」
文化庁「令和6年度 著作権セミナー AIと著作権Ⅱ―解説・「AIと著作権に関する考え方について」―」
AIの生成・利用段階における著作権の考え方
AIを使用して文章や画像などを生成する場合、その利用形態によって著作権法の適用範囲が異なります。
著作権法では、私的使用のための複製は認められており、個人的にAIでコンテンツを生成して利用することには問題はありません。
しかし、生成物を公表したり複製物を販売したりする場合は、通常の著作権侵害と同様の基準で判断されます。
もし、AI生成物が著作権侵害の要件を満たしている場合、著作権者は損害賠償請求や差止請求を行うことが可能です。そのため、AIを活用する際は、利用目的に応じた適切な判断が求められます。
著作権侵害の判断基準について
著作権侵害が成立するか否かは、下記の基準に基づいて判断されます。
他人の著作物の「表現上の本質的な特徴」が直接感得できる場合は類似性が認められます。・依拠性の有無
既存の著作物に接しており、それをもとにした生成物であることが確認される場合、依拠性が認められます。
類似性とは、ある作品が他の作品とどれほど似ているかを評価するものです。特に、既存の著作物の「表現上の本質的な特徴」が他の作品に無断で使用された場合、著作権侵害とみなされる可能性があります。
表現上の本質的な特徴とは、「著作物の独自性や創作性を示す核心的な表現部分」とも言い換えられます。例えば、音楽作品であれば特有のメロディーや和声、文学作品であれば独自の文体や表現方法が該当します。
依拠性は、問題となる作品が既存の著作物に依拠(依存)して作成されたかどうかを示します。つまり、既存の著作物に接し、その内容を知った上で、それをもとに新たな作品が作られたかどうかを判断します。
まず類似性の有無を確認し、類似している場合は依拠性の有無を確認します。通常、この両方が認められる場合、著作権侵害となります。
なお、依拠性がない場合でも、類似性が高いと著作権侵害とみなされることがあるため、注意が必要です。
一方、AI生成物が既存の著作物と類似性および依拠性の両方を欠いている場合、著作権侵害には該当せず、許諾なく利用できます。
ただし、権利者から利用許諾を得ていない場合や、許諾が不要となる権利制限規定が適用されない場合は、著作権侵害に該当する可能性があります。
AIの著作権法違反に関する具体的な事例
AI技術の進歩にともない、生成されたコンテンツの著作権に関する問題が注目されています。下記に、実際に発生した具体的な事例を取り上げて解説します。
これらの事例は、AIの生成物がどのような状況で著作権侵害に該当するのかを理解するうえで参考になります。
事例1|ウルトラマンの類似画像が生成された事例
2024年2月8日、中国の広州インターネット裁判所は、AIが生成したウルトラマンに似た画像が著作権侵害に該当すると判断しました。このケースでは、AIサービス提供事業者が責任を問われることになりました。
裁判所は、生成された画像が著作権で保護されたウルトラマンの独創的な表現を部分的または完全に複製していると認定しました。
生成AIが既存作品の特徴を明確に反映している場合に著作権侵害とみなされることを示す重要な判決といえます。
事例2|生成したAI画像が第三者によって無断使用された事例
SNSに投稿されたAI生成画像が第三者に無断で使用され、著作権侵害が発生した事例も報告されています。著作者が画像に記載していた「透かし」が消去され、無断で流用されたことが問題となりました。
北京インターネット裁判所は、生成された画像が人による独創性を示している場合には著作物と認定され、著作権法による保護を受けると判断しました。この判決では、情報ネットワーク伝達権および氏名表示権の侵害が認められています。
AIの著作権に関する法律に違反しないための対策5選
企業のAI活用においては、著作権問題を避けるために、適切な対策を講じることが重要です。
下記に具体的な5つの対策を紹介します。
対策1|商用利用が可能な生成AIツールを選ぶ
生成AIを選ぶ際には、学習データが著作権フリーであり、著作権侵害リスクの少ないツールを利用することが重要です。
例えば、Adobe社の「Adobe Firefly」は、著作権の懸念がないデータのみを学習しており、安心して商用利用が可能とされています。
導入前に、生成AIツールの公式ウェブサイトで利用規約やライセンス情報を確認し、「商用利用」または「Commercial Use」に関する項目が明記されているかを確かめましょう。
なお、無料版と有料版では商用利用可能範囲が異なる場合があります。有料版の導入を検討することでリスクを低減できることもあります。
対策2|生成物は必ず人間がチェックする
生成AIの出力をそのまま使用すると、著作権侵害のリスクがあるため、人間が必ず確認するプロセスを設ける必要があります。
特に、下記の点に注意しましょう。
・既存の著作物との類似性(特定のキャラ、ロゴ、商標に酷似していないか)
・素材は著作権フリーのものか
・生成AIの利用制限などのルールを遵守しているか
具体的なチェックリストを作成し、生成AIで作成した制作物が必ず一定の基準を満たすようにすることをおすすめします。
このプロセスはGoogleやOpenAIといった生成AI開発企業においても推奨されています。
対策3|専門家にチェックをしてもらう
法律の専門家や著作権に詳しいプロフェッショナルに生成物を確認してもらうことも有効です。専門家に依頼することで、潜在的なリスクを事前に発見し、法的な観点からの具体的な対応策を得ることができます。
ただし、コストが発生するため、企業規模や使用頻度に応じた計画的な対応が必要です。
対策4|社内ルールやマニュアルを作成する
社内で生成AIの使用に関するルールやマニュアルを整備することで、ヒューマンエラーを防ぎ、リスクを軽減できます。
ガイドラインには使用可能な生成AIツールや著作権チェックの手順、問題発生時の報告フローを含めると効果的です。
また、定期的な見直しや研修を実施することも大切です。
対策5|従業員教育を行う
生成AIを使用する従業員に対し、著作権に関する知識や適切な使用方法を教育することは、リスクを低減する上で欠かせません。
社内のリソースが不足している場合は、ぜひeラーニング「SkillBridge」をご検討ください。最短30日で実用的な学びと現場で活かせるスキルが身に付きます。eラーニング形式のため、従業員が場所や時間に関係なく学習を進められるのもメリットです。
SkillBridgeの強みや料金について、詳しくは下記から詳細をご覧ください。
>>SkillBridgeのサービス詳細はこちら
まとめ
AI技術の進化にともない、著作権に関する新たな課題が浮上しています。著作権侵害を回避するためには、生成AIツールの選択や生成物の適切なチェック、専門家への相談、社内ルールの整備、従業員教育の実施が重要です。
これらの対策を実践することで、安全かつ効果的にAIを活用できます。今後のビジネスにAIを取り入れるために、まずは具体的な対策を検討してみてはいかがでしょうか。